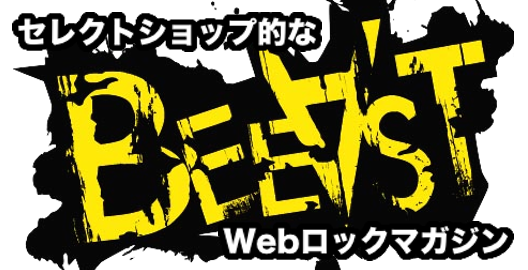FEATURE丨2019.05.09
ROCK ATTENTION 57 扇田裕太郎

国内のロックシーンの最先端を駆け抜け、輝き続けるフロンティアたちの横顔に迫るインタビュー特集「ROCK ATTENTION」。第57回に登場するのは扇田裕太郎(以下扇田)。前作品をリリースした2016年、第45回にも登場している。本特集は2回目の登場となる。
2016年8月にリリースされた『I AM』以来のリリースとなる扇田の2ndソロアルバム『I SING』。シンガー・ソングライター“扇田裕太郎”の独自性を遺憾無く表現した『I AM』は、5曲で完結するコンセプトアルバムとして隙のない完成度を誇っていたが、『I SING』は、同様にバラエティーに富んだ5曲を収録したコンセプチュアルなアルバムながら、『I AM』とは全く異なるフォーマットの音楽を産み出すことに成功している。
本人が語っているように楽曲のクオリティはもとより、ボーカル、ギタープレイでも進化を遂げたこのアルバムは、音楽的に更に自由な広がりを見せながら、聴き手の内面に深く訴える扇田流サイケデリック・ロックの傑作といえるだろう。

http://yagijirushi.com/order/ogidayutaro/
 M01. 銀行強盗
M01. 銀行強盗M02. Different World
M03. 夜空に輝く
M04. Song Song Song
M05. ビートルズになったら
2019年4月9日リリース
URAWA FLOWER RECORDS
UFRC-1002 / ¥1,500(税込)
扇田裕太郎 Official Website
http://ogidayutaro.com/
Live Information
▼2019年5月12日(日)@埼玉森林公園BOSCO
「ゆうたろうトビーの大脱線Part2!」
出演:扇田裕太郎(Vo, Gt) & Tobby(Ds, Vo)
会場:BOSCO
時間:OPEN 17:00 / START 18:00
料金:Music Charge 3,000円
(問)BOSCO 0493-56-5459
埼玉県比企郡滑川町羽尾5286-4
[お申し込み方法]
予約アドレス(お名前、人数、連絡先を書いてメールください)
contactyutaro@yahoo.co.jp
▼2019年5月17日(金)@高円寺ShowBoat
「白浜久プロジェクト2019 ~ 日々是響音元年 東京編」
出演:扇田裕太郎(Gt & Vo)、白浜久(Vo&Gt)、小山卓治(Vo & Gt)、榎本高(Bs & Vo)、西川貴博(Dr & Cho)、多田暁(Tp & Cho)
会場:ShowBoat
時間:OPEN 18:30 / START 19:00
料金:前売5,000円 / 当日5,000円(別途ドリンク代600円)
★前売チケットをご予約、ご購入のお客様には特典CDをプレゼント
(問)ショーボート 03-3337-5745(14:00~23:00)
東京都杉並区高円寺北 3-17-2 オークヒル高円寺 B1
[ご予約お申し込み方法]
・チケット先行販売:2/1(金)~
・ShowBoat店頭(郵送の場合別途580円掛ります)
白浜久オフィシャル(送料が別途¥180掛ります)
チケット一般発売日:2月2日10時~
ローソンチケット
e+(イープラス)
▼2019年5月19日(日)@名古屋植田Laid Back
「扇田裕太郎2ndミニアルバム『I SING』発売記念ツアー!名古屋編」
出演:扇田裕太郎(Vo. Gt)オリジナル曲&洋楽カバー(一人ピンクフロイド他)
時間:OPEN 17:30 / START 18:00
料金:Music Charge 2500円
(問)Laid Back 052-848-7667
愛知県名古屋市天白区原2-202 びい6植田1F
[前売券お申し込み方法]
予約アドレス(ライブ日程、お名前、人数、連絡先を書いてメールください)
contactyutaro@yahoo.co.jp
▼2019年5月20日(月)@大阪梅田ロックバーセブンス
「扇田裕太郎2ndミニアルバム『I SING』発売記念ツアー!大阪編」
出演:扇田裕太郎(Vo. Gt)オリジナル曲&洋楽カバー(一人ピンクフロイド他)
時間:OPEN 19:00 / START 19:30
料金:Music Charge 2500円
(問)ロックバーセブンス 050-3559-9814
大阪市北区曾根崎2-14-10 梅田ロイヤルビル3F
[前売券お申し込み方法]
予約アドレス(ライブ日程、お名前、人数、連絡先を書いてメールください)
contactyutaro@yahoo.co.jp
▼2019年5月24日(金)@下北沢Com.Cafe 音倉
NANKER’S BEST「NANKER’S BEST 3rd Live!!」
『I SING』からの曲、モット・ザ・フープルからの曲、ロッククラシックや即興演奏など
出演:NANKER’S BEST【扇田裕太郎(Vo, Gt) & モーガン・フィッシャー(Keys, Vo)】
会場:Com.Cafe 音倉
時間:OPEN 18:30 / START 19:30
料金:前売3,000円 / 当日3,500円(+1D)
(問)Com.Cafe 音倉 03-6751-1311
東京都世田谷区北沢2-26-23 EL NIU B1F
[前売券お申し込み方法]
予約アドレス(ライブ日程、お名前、人数、連絡先を書いてメールください)
contactyutaro@yahoo.co.jp
▼2019年5月25日(土)@川崎CLUB CITTA’ A’TTIC
「残響天国★扇田裕太郎&森信行プロジェクト!」
『I SING』からの曲を中心にロッククラシックや即興演奏など
出演:扇田裕太郎(Vo, Gt) & 森信行(Ds, Vo)】
会場:CLUB CITTA’ A’TTIC
時間:OPEN 19:00 / START 19:30
料金:Music Charge 3,000円
(問)CLUB CITTA’ A’TTIC 044-244-8100
神奈川県川崎市川崎区小川町5-7 クラブチッタ2F
[前売券お申し込み方法]
ご予約無しでもご入場いただけますが、ある程度の人数確認のため一報いただけると助かります。
contactyutaro@yahoo.co.jp
▼2019年6月5日(水)〜9日(日)@築地ブディストホール
扇田裕太郎が役者として舞台出演
Produced by クイーンズカンパニー
東京倶楽部 公演
「欲望の街 ノットサティスファイド」
出演:杉本愛莉鈴、伴優香、坂本つとむ、小坂正三、扇田裕太郎、他
会場:築地ブディストホール
時間:START 13:00(9日のみ)、14:00(6日と8日)、19:00(5日〜8日)
料金:前売4,500円 / 当日4,800円
(問)築地ブディストホール gekidan.tokyoclub@gmail.com
東京都中央区築地3-15-1 築地本願寺内第一伝道会館2階
[前売券お申し込み方法]
予約アドレス(お名前、電話番号、ご希望日時、予約人数、メールアドレスをご記入の上、御送信ください。)
contactyutaro@yahoo.co.jp

扇田:このアルバムのタイトルはあと付けなんです。出来たものを聴いてみたらボーカル表現に独自なものを感じたのでそういうタイトルにしました。なぜそうなったか振り返ってみれば、そもそも英語で歌うか日本語で歌うかという選択が日本で活動していく上で大きな問題としてあって。英語で歌うと表現できることをなんとか日本語で全うしたいという、日本ロックの永遠の命題というのがあって、そこにここ数年たくさんの時間と思いを割いてきたので、その結果こうしたものが生まれたのかもしれません。
扇田:前作と今作の間にいろんなことがあってミュージシャンとしても進化や変化があったと思いますが、前作と今作の一番大きな違いは作詞作曲のクオリティーと思ってます。今回の作品は全曲が仲間内で始めた『そろそろソロ祭り』というイベントで生まれたものです。作詞作曲を割と気軽に楽しもうという雰囲気で出来た曲達です。作詞、作曲をフィーチャリングしたイベントなので、より実験的だったり野心的だったりするおもしろい曲が増えて結果的にクオリティーが上がったのは嬉しかったですね。
扇田:ライブとレコーディングは常に相互作用があって活かし合ってると思います。でもエフェクターやルーパーというよりは、今回特にkurosawadaisukeと北海道をまわってからは、目の前のお客さん、大切な時間を僕らとの夜に費やしてくれる人たちと何かを共有するという意味でのライブ感を強く意識するようになりました。言い方を変えるならば、『I AM』は永遠がテーマだったのですが、今作は現在(目の前にある今)と永遠を行き来するような立体感がある作品になったと思ってます。
扇田:zellyさんとは特に関係が深いというか、何も言わないでも分かり合えるようなところがあって、ミックスを行ったのが福岡だったのでzellyさんのテイストも入れて欲しいと思ってco-produceのクレジットをしました。ギターも弾いてくれて、どの曲もこれしかないっていう素敵な世界をプラスしてくれています。この作品におけるzellyさんとミックスをしてくれた立川さんの功績は巨大です。
扇田:こういった特色ある楽曲たちなので、歌もギターも世界を創ることが一番大事。狙った世界を表現できてるか、体現できてるか、が全てでした。世界が創れたと感じた2、3テイクを送って、あとはzellyさんと立川さんに任せました。

扇田:いわずもがなですね。英語のスイング感を日本語でどう表現しようか実験してるときに、ボブ・ディランの歌い方って面白いと思うようになって。喋ってるような歌いまわしの印象が強いですが、実はすごく音楽してるんですよね、ディランって。特に言葉のスイングさせ方が半端ない。その感覚を日本語でやろうと試していくうちに何かあまり聴いたことないスタイルというかオリジナリティが生まれた気がしたので収録しました。ややドライと感じるのは日本語なのに言葉の意味を歌っていないからだと思います。これまでも何度かインタビューで語ってきたことですが、意味は聴き手に委ねるのが一番と思ってますし、それはおっしゃる通りで普遍的な作品であって欲しいからです。
扇田:ありがとうございます。自信作です。ライブでやるの超難しいんですけど(笑)
扇田:根源的な美を持った名曲!すごい嬉しいです。そして、ああ、なるほど。進化の行き着くところに“個”があるというのは第1段階としてはとても納得がいくもので、だからこそ僕の作品は“I”シリーズになってるとも言えます。「Different World」という曲は『I AM』から一歩踏み出て、自分とは違う宇宙があることを認める宣言です。でもそれを認めるのは“I”なんですよね。“I”から踏み出す“I”。ジャケットは実はDeeDriveの池崎氏が何も言わずにあれを創って来たんですよ。zellyさんや立川さんと一緒でテレパシーかなんかで繋がっているんだと思います。
扇田:ああ、そうかも知れませんね。それは嬉しい意見です。実験的なことも含めて作詞作曲で好き放題やったからこそルーツが見えて来たのかもしれませんね。飛び込もうと思えば思うほど正直さが必要だったりするので。僕はピンク・フロイド、レッド・ツェッペリン、デビッド・ボウイ、ビートルズという結局王道が好きなのですが、似てしまうとどうしても避けてしまう傾向なので、それでもルーツが見えると言ってもらえるのは最高に嬉しいです。
扇田:この曲は、言っちゃうとつまらないかもしれないですが、どうにもならないことや人生の切なく苦い経験のセレブレーション、つまりお祝いです。それをお台場の華火で慰霊するという。実は東京湾華火大会を毎年船から見るイベントを主催し続けてきて、僕にとって特別な意味がある華火なんですね。(注:東京湾だけ花火ではなく華火と書く)この華火はそもそも東京大空襲の慰霊の意味を込めて開催されていたという経緯があるので。華火と共に思いを爆発させて消滅させるんです。僕らはいろんな経験するために生まれてきたんだっていう。だからこそ人生は尊いと思ってます。

扇田:ありがとうございます。そう。「夜空に輝く」良いですよね。これまでにあまりなかったタイプの曲が創れたと思ってます。レコーディングは、他の曲同様とにかく世界をしっかり描くことですね。それとあのディレー発振はzellyさんなんですよ。いつも僕がやってるディレー発振とアプローチが違うのが面白くて。僕も相当ディレー好きですがあの人ディレーの魔術師なので。
扇田:そうですね。東北ツアーではラストにこの曲をやりました。中間部で長いディレーかけたりトレモロマックスにしたり、ラストはルーパーでソロ弾いたり。でもこれからまだまだ展開できそうですね。いずれzellyさんとディレー発振の共演とかもやれたら面白いかも。華火二発!(笑)
扇田:本質を追求する感じに伝わってるのは嬉しいですね。時代はあまり考えてません。どうなんだろう?いつ何が響くかっていうのはわからないので、自分が大好きで夢中になれることに没頭するくらいしか道はないと思ってて。そういう意味ではすごく自分らしい音楽が創れたと思ってます。脱却感も含め。一度きりの人生ですからね。
扇田:なるほど。90年代のブリティッシュロックというとオアシス、ブラー、スエード、レディオヘッド、クーラシェイカーとかあとシャーラタンズとかストーン・ローゼズとかトラビスとかだと思うのですが、僕はちょうどそういう人たちとほぼ同年代なんですよ。ローゼズはちょっと上かな?聴いてきた音楽も近いしやっぱり時代の空気とかってあると思います。僕は85年から89年までロンドンに住んでたので土壌ができあがる時期も重なりました。みんなその時期の英国のインスピレーションが90年代に入って開花してると思うので。だからそういったバンドの音楽には今でもシンパシーを感じますね。
扇田:そうなんですよ。モーガンとは去年知り合って秋頃からものすごいペースでセッションとサシ飲みを繰り返しました。60年代から70年代にかけてのロンドンのロックシーンのど真ん中にいた人ですから、ジミー・ヘンドリクスを小さなクラブで最初に観た時の話しとか、その時から「Purple Haze」演ってたとか、キース・ムーンの家にしょっちゅう遊びに行ってたとか、ロックアイコンがみんな集まるBARに入り浸っててシド・ビシャスに絡まれた話とか、僕にとっては全てが雑誌や映画でしか観たことがない世界で、モーガンと音を出すことで、モーガンと乾杯することで、それらがリアルな現実として意識の中に形作られる体験をしました。モーガンってロックから早々に離れてインドに渡ってグルの元で人生を学んだ生粋のロックアイコンなんですね。そして即興へ没頭していった。そんなミュージシャンがこんな身近にいるのは奇跡だと思ってますし、僕の音楽や人間性を気に入ってくれたことは自信にもなりました。本当に、得たものは多大ですし、このアルバムにも反映されてると思います。今モーガンはモットでアメリカとイギリスツアー中ですが、帰ってきたらまたすぐNANKER’S BESTでもライブやるの楽しみですね。

扇田:『I AM』で自己の確立を達成して“私は在る”という気づきに至っても、結局何かを達成するためには一歩踏み出さなければならないわけだし、歌うためには曲を創らなければならない。この曲では第一次的創造であるプライマリー、そしてオリジナルソウル、こそがパーフェクトゴールだと歌ってます。オリジンというのは起源のこと。音楽の故郷を賛美するような曲と思ってます。
扇田:英語の歌だけど、日本人でもみんなすぐわかってくれて一緒に歌えたりしたら良いなと思ってSong Song Song という歌詞から作詞を始めました。3つ並べたのもそんな感じです。すぐ覚えられる(笑)でも良く読むと内容は深い、という曲になりました。
扇田:僕もそう思ってます。なんでこんな曲ができたんだろう?(笑)
扇田:僕は何かになりたいと思ったら、なりきっちゃうのが一番だと思っていて。音楽家になるのに資格なんていらないし、ビートルズになるのだってそう。なりきっちゃうのが一番って思ってみたり。楽しい想像ですよ。“銀行強盗”と一緒です。夢と現実の境目に僕ら生きてますから。
扇田:あ、いや。悲哀なんてわからないんです。悲哀すらも憧れなんです。普通の生活がしてみたいと言ってみたいんです(笑)

扇田:そうなんですよね~。なんでこんな曲ができたんだろう?
扇田:『そろそろソロ祭り』を一緒にやってる910ちゃんという最近アコギの弾き語りも始めたベーシストの友達がいて。歌うkeyの特定をどうやって決めてるかと質問されて、いろいろ答えてるうちに発想の囚われに気づいてしまったんです。合わないキーで歌った方が面白い曲もあるかもって思ったり。それで実験を開始してあっという間に出来たのがあの曲です。やっぱり何か新しいものが生まれる瞬間というのは気づきがあるとき、そしてシリアスにならずに、でも真剣で遊び心がある時なんですよね。
扇田:ギターの表情が豊かなのはzellyさんが参加してくれたおかげだと思います。特に「ビートルズになったら」の浮遊ギター、素晴らしいですよね。あとは「銀行強盗」のサイケアルペジオと「夜空に輝く」のトレモロと発振ディレーとかもzellyさんです。アルバムのカラーを決定づける大事な役割をやってくれました。僕のギターでは「ビートルズになったら」のアルペジオができたときはキタと思いました。アルペジオだけでソングになってるんですね。そういう曲ってあるじゃないですか。あとお気に入りは「Song Song Song」のギターソロ。“Destroy the fence”という歌詞に応えてジョキンとフェンスを切るサウンドから入る(笑)あと「Different World」のラストのソロはすごく僕らしいですね。指弾きでチョーキングのうにょっとした感じ。まあでもやっぱり自分じゃない世界が加わることって大事なんで、今回ギターはzellyさんのテイストが入ったことは大きいです。2つの世界が溶けて新しい世界が生まれた。と「Different World」でも歌ってるとおりですね。
扇田:僕はソロ活動だけでもこんな多種多様なのに、他にも原始神母やThe Day Sweet、モーガン・フィッシャーとのNANKER’S BESTや冨田麗香&ザ・ローリングジプシーズ、いろんなプロジェクトをやってるから良く言われるんですよ。“扇田裕太郎”は一体何者なのか?と。いろいろやり過ぎでわかりづらいと言われることもあります。“扇田裕太郎”のスタイルとは何なのか?そこで、ならばスタイルとは一体何を指すのか?と逆に僕は問いたい。スタイルというのはフランス語のスタイロ(stylo)から来ていてその語源はラテン語のスタイラス(stylus)だと思うのですが、つまり筆跡のようなものだと思うんですね。みんなサインを書くときに自分らしさをアピールしようとか、こんな感じでとか考えないじゃないですか。サイン(筆跡)というのは自分らしさの最たるものとして契約などに使われるにもかかわらず、こちらから自分らしさを発揮する必要などないほどに根本的に自分らしいんですね。僕にとって音楽もそういうものと思ってます。90年代UKでいこう、とかパンクで、とか、次はプログレ、とか全く考えてません。ツェッペリンが3で突如アコースティックやってもどうしようもなくツェッペリンでしかないわけで、ビートルズやピンク・フロイドのように限定からはみ出るアーティストの音楽が僕は好きなんですね。だから僕が何をやろうが僕として僕で在る限りは僕なんです。ただ僕として在ることがどれほど難しいことか、と『I AM』で歌いました。この『I SING』はその続きと言えます。
扇田:これは僕のメインプロジェクトでありライフワークですから、死ぬまで活動を続けることが最大の目標です。夢は宇宙が一つの生命体として感じられるようなスペースを創り出すことです。何言ってるんだ?と思うかもしれませんが、ビートルズやピンク・フロイド聴いていると、たまにそういう感じになるんですよね。そういうことを頻繁にやれるアーティストになりたい。

【特集】ROCK ATTENTION 45 扇田裕太郎
https://www.beeast69.com/feature/157147
【特集】ROCK ATTENTION 53「The Day Sweet」
https://www.beeast69.com/feature/174041
【特集】BEEAST太鼓判シリーズ第42弾「冨田麗香」
https://www.beeast69.com/feature/161376